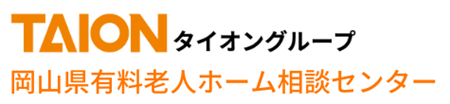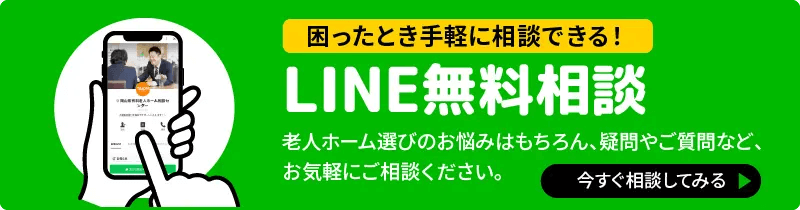「知って安心」介護に関する基礎知識
高齢化が進む社会の中、「介護」はある日突然身近な存在になります。「自分はまだ関係ない」と考えるのではなく、介護について基本的なことを知っておけば、もしもの備えになります。
ここでは、各種高齢者向け施設・住宅の違いや、入居前に知っておきたいお金のことなど、専門家監修のもとジャンルごとに分かりやすくまとめています。
お役立ち情報
介護保険の自己負担額はいくら?

いざ介護保険を利用するとなると、一番気になるのはやはり自己負担額ではないでしょうか。
介護保険の自己負担額は介護サービス料金の割合で決まっています。
今回は、介護保険の利用時の自己負担額を中心に解説していきます。
基本的な介護保険負担額は1割
介護事業者が提供するサービスへの対価は、介護保険の保険者である市町村による給付と、被保険者である介護利用者の自己負担額で支払われます。
介護利用者の自己負担額は、基本的に1割負担です。
例外としては、以下のように65歳以上で、ある程度所得が見込まれる方に関しては、2割・3割の負担となります。
介護保険が3割負担に当てはまる条件
本人の合計所得金額が220万円以上 かつ 本人を含めた同一世帯の65歳以上の人の「年金収入+年金以外の合計所得金額」が一人の場合で340万円以上、2人以上いる場合で合計463万円以上
介護保険が2割負担に当てはまる条件
本人の合計所得金額が160万円以上 かつ 本人を含めた同一世帯の65歳以上の人の「年金収入+年金以外の合計所得金額」が一人の場合で280万円以上、2人以上いる場合で合計346万円以上
※遺族年金・障碍者年金については所得とみなされません
自分の負担割合を確認する方法
被保険者である方が実際どの割合が自己負担となるのか、一番早く確認できる方法は、「介護保険負担割合証」を見ることです。
「介護保険負担割合証」は、介護保険の申請時に発行されるもので、被保険者の自己負担割合が記載されています。
「介護保険負担割合証」は、1年ごとに更新され、8月から翌年の7月までが有効期限となります。なので、介護保険が適用されると毎年7月に更新された「介護保険負担割合証」が送られてきます。
注意!介護保険の給付額には上限額がある
介護保険があるから、どんな介護サービスを利用しても1割のみの負担で済む・・・訳ではないのです。
在宅サービス・介護予防サービスには給付額の上限額があり、それを超過すると、超過分は全額自己負担額に上乗せして支払わなければなりません。
以下は支給限度額の目安です。要介護度によって異なります。
| 要介護度状態区分 | 支給限度額の目安(1か月) |
|---|---|
| 要支援1 | 50,320円 |
| 要支援2 | 105,310円 |
| 要介護1 | 167,650円 |
| 要介護2 | 197,050円 |
| 要介護3 | 270,480円 |
| 要介護4 | 309,380円 |
| 要介護5 |
362,170円
|
※支給限度額に含まれないサービス
●居宅療養管理指導 ●認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く) ●特定施設入居者生活介護(短期利用を除く) ●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ●地域密着型特定施設入居者生活介護 ●特定福祉用具販売(支給限度基準額1年間10万円) ●住宅改修費支給(支給限度基準額20万円)
自己負担額を軽減させる方法がある
高額介護サービス費
給付額に上限額が設けられている、というお話をしましたが、自己負担額にも上限額が設けられており、その上限を超過した場合はその分払い戻しを受けることができます。
上限は以下のとおりです。
| 利用者負担段階区分 | 上限額(世帯合計) |
|---|---|
|
市民税課税世帯 かつ
課税所得690万円以上
|
140,100円 |
|
市民税課税世帯 かつ
課税所得380万円以上690万円未満
|
93,000円 |
|
市民税課税世帯 かつ
課税所得380万円未満
|
44,400円 |
|
市民税非課税世帯 かつ
下記以外
|
24,600円 |
|
市民税非課税世帯 かつ
課税年金収入額およびその他の合計所得金額の合計が80万円以下の人
|
15,000円 (個人上限額) |
|
市民税非課税世帯 かつ
老齢福祉年金受給の人
|
15,000円 (個人上限額) |
| 生活保護受給の人 | 15,000円 (個人上限額) |
対象となった場合は、「高額介護サービス費等支給申請書」を提出すると適用されます。
高額介護合算療養費制度
高額介護合算療養費制度とは、介護保険サービスと医療保険サービス、両方に自己負担額が発生し、その合計額が年間(8月~翌年7月)の所定限度額を超えた場合は、医療保険の窓口へ申請することにより年間のサービス利用後に超過額が支給される制度です。
【70歳未満の場合】
| 所得額 | 限度額 |
|---|---|
| 901万円以上 | 212万円 |
| 600万円以上901万円以下 | 141万円 |
| 210万円超600万円以下 | 67万円 |
| 210万円以下 | 60万円 |
| 住民税非課税世帯 | 34万円 |
【70歳以上・または後期高齢者医療被保険者の場合】
| 所得額 | 限度額 |
|---|---|
| 課税所得690万円以上 | 212万円 |
| 課税所得380万円以上 | 141万円 |
| 課税所得145万円以上 | 67万円 |
| 一般 | 56万円 |
| 低所得者Ⅱ | 31万円 |
| 低所得者Ⅰ | 19万円 |
介護保険が適用される施設へ入居をご希望の方へ
今回は介護保険の自己負担額についてご紹介しました。いかがでしたでしょうか?
介護保険は年齢や所得によって該当区分や負担額も変わるため、申請や施設選びに時間がかかる・・・という方も多いのではないでしょうか。
そんな方のために、岡山県内に特化した【岡山県有料老人ホーム相談センター】は窓口を開設しております。県内の施設と連携して、持病や費用に合った老人ホームをご紹介しておりますので、一度是非お気軽にご相談ください。

監修者:山本晃
2015年8月入社。株式会社タイオン365立ち上げメンバー。 老人ホーム相談事業の相談員として4年間勤務。計820名のお客様をご案内させていただきました。その後、2020年8月から介護保険事業へ参入。デイサービスを3施設、2021年9月に福祉用具貸与販売事業を開設。その他に介護施設コンサルをさせていただいており、集客や運営のお手伝いをさせていただいています。